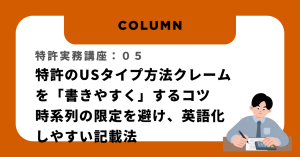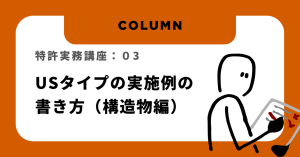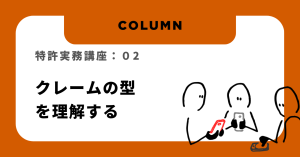Last Updated on 2025-07-01 by matsuyama
弁理士の日記念ブログ企画2025 参加ブログです!
https://benrishikoza.com/blog/benrishinohi2025/
生成AIに仕事を奪われるぅ!
どの業界でもよく聞く話ですな。
確かに、どんどん生成AIにとって代わられているところはあると思います。
そもそも、私が弁理士業界に入ったのは今から30年以上前の話。
その当時は、ワープロ専用機全盛期です。
まだ、Windows95が世に出る前ですから。
その頃は、タイプ屋さんがいました。
手書きの原稿を渡すとタイプしてデータ納品してくれるのです。
図面屋さんも必ず頼んでいましたね。
これはデータではなく、紙納品でした。
図面用に文字テンプレートや雲形定規は必須でした。
今までも技術の進歩、特にOAの進歩に伴っていろんな職種がなくなっています。
でも、なんか今回の生成AIは雰囲気が違います。
なんだか、人と同じことができるような感じがするのでしょうか?
AIは!
この仮説が正しいとすると、もう人はいらないよ! ということになるのでしょう。
そんな恐怖感が人にあるのでしょう。
まあ、確かに数十年後、早ければ10~20年後には、人間並みにものを考えて行動するAIが登場するかもしれません。
しかし、現状ではそこまではいっていませんね。
人とAIとでは役割分担があるみたいです。
Gemini先輩に「知財業界におけるAI」を聞いてみました。
「人間とAIの役割分担の原則
基本的には、以下のような役割分担が考えられます。
• AIの強み:
膨大なデータの高速処理・分析
パターン認識・異常検知
定型的・反復作業の自動化
多様な選択肢の網羅的な生成
客観的データの提供
• 人間の強み:
創造性、独創性、ひらめき
倫理的判断、社会性、文化理解
複雑な状況判断、曖昧さへの対応
交渉、コミュニケーション、人間関係構築
法的解釈、戦略的思考、責任
生成AIは、人間の知財活動を代替するのではなく、あくまで人間の知的活動を拡張し、支援する「賢いツール」として機能することで、より効率的で、より高度な知財の創造、保護、活用が実現されると考えられます。この協力関係は、知財業界に大きな変革をもたらすでしょう。」
と、まあこんな答えが帰って来ました。
要は、「人間よ。AIをうまく使えよ」と言ったところでしょうか。
ところで、知財業界とはどんな業界でしょうかね?
我々弁理士は知財業界をゆがめている張本人だと、常々思っています。
なぜって、知財業界=法律実務界隈と思っているし、それを実践しているから、です。
でも、本当は、知財はビジネスの基であり、創出→保護→活用のサイクルを回すことが知財活動だと思います。
だとすると、知財業界=ビジネスそのもの、と言えませんか?
知識を作り出して、活用することで利益を生み出す。
まさにビジネスです。
そして、利益状態を維持するために、保護活動を行う。
その一部が権利化業務なのです。
確かに権利化業務に絞って見ると、AIは活用のし甲斐があるでしょう。
オープンなものは、新規性の喪失の問題があるので使いづらいですが、クローズドのAIシステムは活用するべきでしょうね。
特に方式ではAI活用が進むと思いますし、補助業務は今ほど人が必要ではなくなるかもしれません。
でも、逆に新しいビジネスチャンスがあります。
方式AIアプリを作れば売れるかもしれません。
一つ作ると、他の士業用のものも作れそうです。
文書作成のAIにしてもそうです。
特化したものなら売れそうです。
プログラミングなんて作れない、と思ってもアプリの上流設計にかかわったり、なんならそれこそAIに書いてもらってもいいですよね。
仕事って、便利になったらなったで、また新しいものが必要になる。
その繰り返しですよね。たぶん。
まとめると、絶えず、アンテナを張っていないとくいっぱぐれる! ことだけは確かなように思うのです。
ではでは