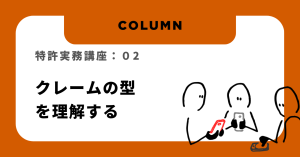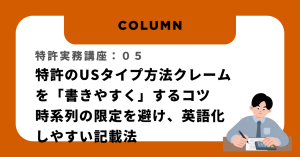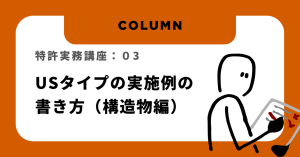Last Updated on 2025-12-17 by matsuyama
特許明細書を書く上で、最も重要なスキルのひとつが「クレーム(特許請求の範囲に記載された請求項)に応じた実施例を書く力」です。これは単なる文章力ではなく、発明の本質を理解し、それを具体的に表現する力を意味します。
第1段階では、この力を養うための基礎を学びます。
まず、クレームの型とそれに応じた実施例に必要な記載とを理解し、具体的に記載できるようにしましょう。
この項において、「実施例」とは、後述する発明の実施の形態に記載される内容(embodiment)と、特に化学分野に多用される実施例(example)を総称するものです。
おすすめの方法は、既存の特許公報からクレームを見て、それに合わせて実施例を書いてみることです。実務外でも時間が取れるなら、ぜひ挑戦してみてください。
クレームから実施例へ
クレームは、発明の権利範囲を定める最も重要な部分です。
実施例は、そのクレームに基づいて発明の具体的な形態を示すものであり、審査官や第三者に発明の内容を理解させる役割を担います。
実務においては、クレームを見た瞬間に「どんな実施例を書くべきか」が頭に浮かぶようになることが理想です。これは一朝一夕では身につきませんが、型を理解し、トレーニングを重ねることで確実に習得できます。
明細書の基本構成を押さえる
特許庁が定める明細書の記載項目は以下の通りです:
- 【発明の名称】
- 【技術分野】
- 【背景技術】
- 【先行技術文献】
- 【発明の概要】
- 【発明が解決しようとする課題】
- 【課題を解決するための手段】
- 【発明の効果】
- 【図面の簡単な説明】
- 【発明を実施するための形態】
- 【実施例】
- 【産業上の利用可能性】
このうち、【発明を実施するための形態】と【実施例】が、実際に発明をどう実現するかを記載する部分です。特に化学分野では【実施例】が重視されます。
この項目を見て気づくことはありませんか?
そうです。発明の流れを示しています。
従来の問題点→課題の発見→解決手段の提案→それにより得られる効果→具体例
そうなっています。そのうちの具体例を書くのが実施例の欄になります。
クレームには「型」がある、ならば実施例にも?
クレームの書き方には一定の「型」が存在します。これは長年の先人の実務の積み重ねの上に作り上げられたものです。したがって、この型を理解し、使えるようにすることは重要です。
そして、このクレームの型に応じて、実施例の記載の型があります。
第1段階では、以下の6つの型を学びます:
- USタイプ(要素列挙方式)
- ジェプソンタイプ(プリアンブル方式)
- マーカッシュ型
- パラメータ型
- プロダクト・バイ・プロセス型
- 機能的クレーム
これらの型と発明のカテゴリー(物、方法、物の製造方法)との関係性を理解することで、実施例の記載力が飛躍的に向上します。
まとめ
第1段階では、「クレームの型を理解し、それに応じた実施例を書く力」を養うことが目的です。明細書の構成を押さえ、型ごとの特徴を理解し、実際に書いてみることで、特許実務の基礎力が身につきます。
次回は、クレームの「型」について、6つの代表的な形式を詳しく解説していきます。