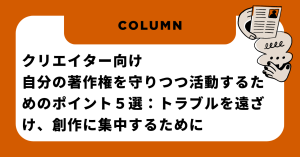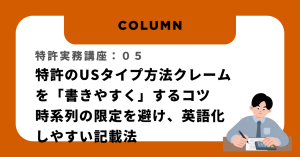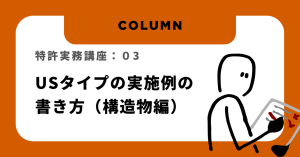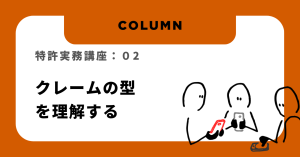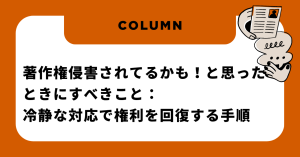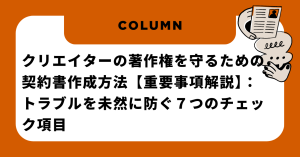1.著作権の基本構造:二つの柱「財産権」と「人格権」
著作権法は、著作物を創作した者(著作者)の利益を保護するために存在します。この保護の対象は、「財産的な利益」と「人格的な利益」の二つです。
著作財産権(財産的な利益を守る権利)
著作財産権は、作品を利用して金銭的な利益を得るための権利の総称です。この権利は譲渡や相続が可能であり、売買することができます。一般的に「著作権」という言葉を使う場合、この著作財産権を指すことが多いです。
- 経済的価値:この権利を他人に許諾(ライセンス)したり譲渡(売却)したりすることで、対価(使用料や報酬)を得ることができます。
- 集合体:単一の権利ではなく、後述する複数の権利(支分権)の集合体です。
著作者人格権(人格的な利益を守る権利)
著作者人格権は、作品に込められた著作者の精神や名誉を守るための権利です。この権利は著作者本人に一身専属するため、他人に譲渡したり相続させたりすることは一切できません(著作権法第59条)。
- 非譲渡性:仮に著作財産権をクライアントにすべて譲渡したとしても、著作者人格権は永遠にクリエイター本人に残ります。
- 目的:作品の公表や改変について、著作者の意思を反映させることを目的としています。
2.著作財産権に含まれる具体的な「支分権」
著作財産権は、著作物の利用形態ごとに細かく権利が分かれています。これらの権利はすべて、譲渡する際に個別に特定するか、包括的に譲渡するかを定める必要があります。
① 複製に関する権利
- 複製権:著作物を印刷、写真、録音、録画、またはデジタルデータとしてコピーする権利。Web上の画像ダウンロードなどもこれにあたります。
② 公衆への伝達に関する権利
- 上演権・演奏権・上映権・展示権:作品を公の場所で発表する権利。
- 公衆送信権:インターネットのストリーミング配信、アップロード、テレビ放送など、公衆へ向けて情報を送信する権利。
③ 流通に関する権利
- 譲渡権・貸与権:作品の複製物(書籍、CD、ゲームソフトなど)を販売したり、レンタルしたりする権利。
④ 二次的利用に関する権利【特に重要】
- 翻案権(ほんあんけん):作品を土台として、新しい創作を加えた別の著作物(二次的著作物)を創作する権利。
- 例:小説を映画の脚本にする、イラストをキャラクターグッズのデザインに利用する、楽曲を編曲する。
- 二次的著作物の利用権:翻案権によって作られた二次的著作物(例:映画)を、元の著作権者が利用できる権利。
3.著作者人格権を構成する3つの権利
譲渡できない著作者人格権は、クリエイターの精神的な利益を守るために特に重要な権利です。
権利1:公表権(著作権法第18条)
著作者が、未公表の著作物を「公表するかどうか」「いつ、どのような方法で公表するか」を最終的に決定できる権利です。クライアントが未完成の作品を勝手に公開したり、事前の合意と異なる形で発表したりすることはできません。
権利2:氏名表示権(著作権法第19条)
著作者が、自分の作品に「実名」を表示するか、「ペンネーム」を表示するか、あるいは「氏名を表示しない」かを決定できる権利です。クライアントは、著作者の意思に反して勝手に氏名を非表示にしたり、逆に表示したりすることは原則としてできません。
権利3:同一性保持権(著作権法第20条)
著作者が、自分の意に反して著作物の内容、題号(タイトル)、形式を勝手に改変されない権利です。
- 重要性:クライアントワークにおいて、発注元の都合で作品の配色や構図、文章などが修正される際、この権利が問題となることがあります。
- 例外:誤字脱字の修正、プログラム言語の変更など、法令や契約上の改変、性質上やむを得ない改変は、この権利の侵害にあたらないとされています。
4.契約書に絶対記載すべき2つの重要ポイント
業務委託契約書や著作物利用許諾契約書を作成・確認する際、この2つの著作権に関する条項を曖昧にすると、将来大きなトラブルに発展します。
ポイント1:著作財産権の「譲渡範囲」を明確にする
著作権(財産権)をクライアントに譲渡する場合、譲渡する権利の範囲を明確に特定することが不可欠です。
【危険な記載例】
❌「本著作物に関する著作権はすべて甲(クライアント)に帰属する。」
【推奨される記載例】
✅ 「本著作物(成果物)に関する著作権法第21条から第28条に定める権利(同法第27条及び第28条の権利を含む)は、著作物(成果物)の納品完了時に乙(※クリエイター)から甲に移転するものとする。」
- なぜ27条・28条の明記が必要か:これらの権利(翻案権、二次的著作物の利用権)は、包括的に「著作権を譲渡する」と記載しただけでは譲渡されないと推定されているため(判例による解釈)。クライアント側としては、将来的なリメイクや多角的な利用のために、この2つの権利が必須です。クリエイター側としては、この権利を譲渡すると、作品の二次利用を完全にコントロールできなくなるため、対価をしっかり交渉すべきです。
ポイント2:著作者人格権の「不行使特約」をどう扱うか
譲渡できない著作者人格権について、実務上はクライアントが作品を自由に利用・修正できるように、「著作者人格権を行使しない(不行使)」という特約を結びます。
【一般的な契約書記載例】
✅ 「乙(クリエイター)は、甲及び甲から許諾を受けた第三者に対し、本著作物に関する著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとする。」
クリエイター側の交渉ポイント:
-
- 「軽微な修正に限る」などの限定:「著作者の意図を著しく損なう改変については除く」など、同一性保持権の不行使を限定的にするよう交渉する。
この場合、上記の文章に続けて「ただし、著作者の意図を著しく損なう改変については除く。」等記載します。「著作者の意図を著しく損なう改変及び公序良俗に反する改変については除く。」等バリエーションをもたせることもできます。 - 氏名表示の義務化:「氏名表示権の不行使」を承諾する代わりに、著作物を利用する際には必ずクリエイター名を明記することを契約上の義務として盛り込んでもらう。
- 「軽微な修正に限る」などの限定:「著作者の意図を著しく損なう改変については除く」など、同一性保持権の不行使を限定的にするよう交渉する。
- 重要性:クリエイターは、不行使特約を結ぶことで、報酬以外の精神的対価を諦めることになるため、この点も報酬交渉の材料とすべきです。
5.【補足】著作権の保護期間とパブリックドメイン
著作財産権には保護期間が定められています。
- 原則:著作者の死後70年まで。
- 法人著作物:公表後70年まで。
保護期間が終了すると、著作財産権は消滅し、著作物はパブリックドメイン(公共の財産)となり、誰もが自由に利用できるようになります。
ただし、著作財産権が消滅しても、著作者人格権は著作者の死後も存続し、著作者の名誉や声望を害するような利用は禁止されています(著作権法第60条)。
【まとめ】契約書は未来の作品利用のルールブック
著作権は、クリエイターにとっての生命線であり、ビジネスの根幹です。特に著作財産権と著作者人格権の違いは、単なる知識ではなく、契約時に自分の権利をどう守り、どう売るかという戦略に直結します。
契約書は、作品が将来どのように利用されるかを決める「ルールブック」です。安易な気持ちで「著作権譲渡」や「著作者人格権不行使」の条項に同意する前に、譲渡範囲(27条・28条の有無)と人格権の取り扱いを必ず確認し、その対価として報酬が十分か吟味しましょう。必要に応じて、専門家に相談することが、トラブルを防ぐための最善策です。