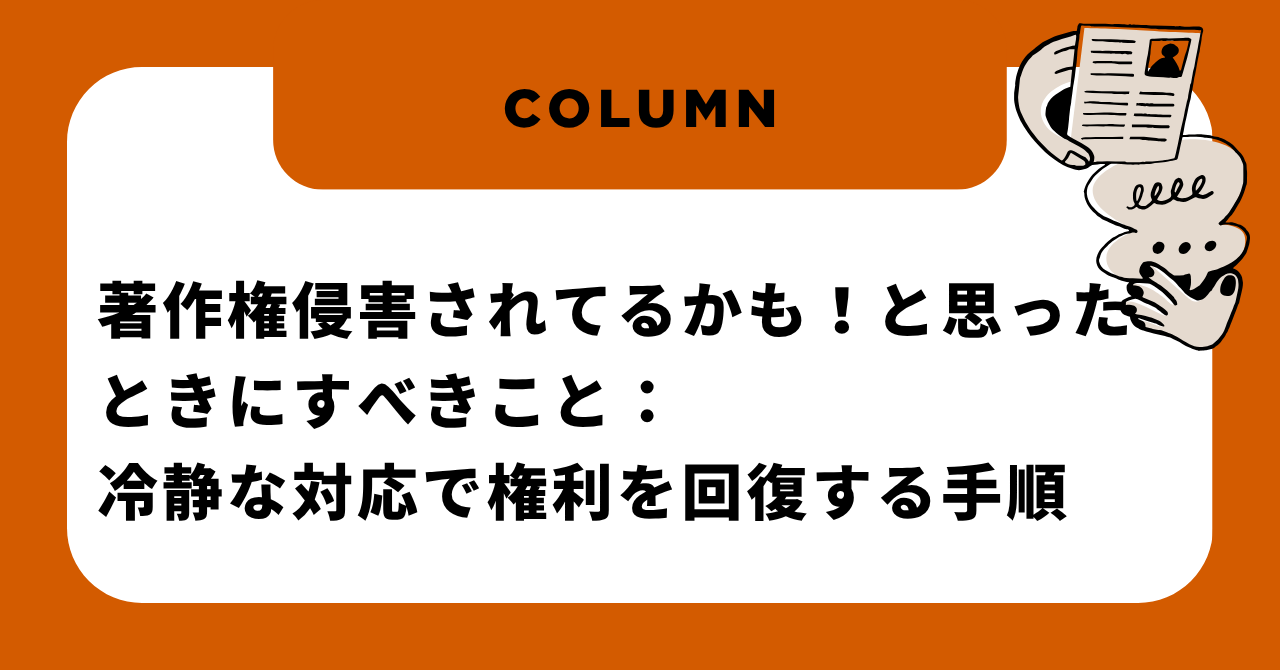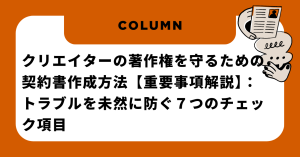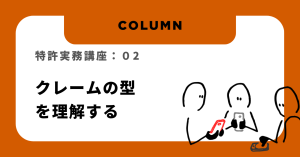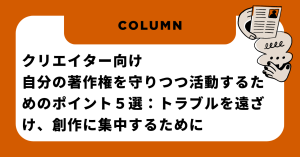Last Updated on 2025-11-07 by matsuyama
ネット上で自分の作品と酷似した画像や文章を見つけたとき、動揺するのは当然です。しかし、感情的に行動するのではなく、冷静かつ手順通りに対応することが、権利回復と損害の最小化への最短ルートです。「侵害されたかも?」と感じたクリエイターが、最初に行うべき5つのステップと、具体的な対処法について解説します。
ステップ1:まずは「著作権侵害」に該当するか冷静に確認する
「似ている」と感じただけでは、著作権侵害とは限りません。法的措置に進む前に、以下の2つの要件を満たしているかを客観的に確認しましょう。
1.依拠性(イキョセイ)の有無
相手の作品が、あなたの作品を「見て・知って」制作されたものかどうか。偶然の一致(独立創作)であれば、著作権侵害は成立しません。ただし、有名な作品であれば「知っていた」と推定されやすいなど、立証は難しい場合もあります。
2.類似性の有無
相手の作品が、あなたの作品の**「創作的な表現」**(単なるアイデアや事実ではなく、作者の個性が表現されている部分)と似ているかどうか。以下の場合は類似性が認められず、侵害にあたらない可能性があります。
- アイデアの模倣:「青い空と白い雲の絵」というアイデア自体には著作権はありません。
- ありふれた表現:「定型文」や「シンプルな図形」など、誰が書いても同じになる表現には著作権は認められません。
- 著作権消滅作品の利用:著作者の死後70年が経過した作品(パブリックドメイン)は自由に利用できます。
特に「トレパク(トレースしてパクる)」の場合は、依拠性と類似性の両方が容易に認められやすく、著作権侵害となる可能性が高いといえます。
ステップ2:著作権侵害の「証拠保全」を徹底する
侵害者に連絡を取る前に、必ず最初に行うべき最重要ステップです。相手が証拠を隠滅したり、コンテンツを削除したりする前に、現在の利用状況を記録します。
記録すべき事項と方法
- 侵害コンテンツのURL:正確なWebアドレスを控える。
- 日時:スクリーンショットや動画を撮った日時を記録する。(法的な証拠力のために公的なタイムスタンプを取得することも検討)
- 利用形態:どのように利用されているか(例:そのまま複製されている、一部改変されている、販売されているなど)を詳細に記録する。
- **侵害サイトの所有者情報:**可能であれば、サイトの管理者情報(Whois情報)を検索し、控えておく。
証拠を撮り忘れると、後に「そのような事実はなかった」と反論された際に、あなたの主張が通らなくなる可能性があります。
ステップ3:侵害者に「削除要請」や「警告文」を送付する(専門家への依頼を含む)
証拠を保全したら、具体的なアクションに移ります。
直接交渉(Eメールなど)※第三者や専門家への相談も
相手の連絡先がわかる場合は、感情的にならず、以下の内容を記載した簡潔なメールを送ります。
また、直接交渉の前に、第三者への相談や専門家のアドバイスを求めに行くことも検討します。
- どの作品のどの部分が(あなたの作品のURLを添えて)、どこで(侵害コンテンツのURLを添えて)、どのように侵害されているか。
- 著作権法違反にあたるため、〇日以内にコンテンツを削除し、利用を停止するよう求めること。
- 削除に応じない場合、法的措置やプラットフォームへの削除申請に進む可能性があること。
⚠️SNS等を通じて、著作権侵害を行ったとして特定の相手の情報を公開し、非難を煽るような行為がなされることがあります(「晒し」と呼ばれる行為)。これは晒す行為をした側が法的責任を問われることもある大変危険な行為です。こうした私刑に走るのではなく、あくまでも冷静な対応を徹底することが重要です。直接交渉が難航する場合は、まずはお近くの専門家や法テラス等にご相談ください。
内容証明郵便の利用(専門家に依頼)
相手が法人や連絡が取れない場合、または交渉を有利に進めたい場合は、行政書士や弁護士に依頼して内容証明郵便を送付します。これは、法的な圧力をかけるとともに、警告した事実とその内容を郵便局が公的に証明してくれるため、後の裁判で重要な証拠となります。
ステップ4:プラットフォーム(サイト管理者)に「削除申請」を行う
相手が直接の警告に応じない場合や、匿名で連絡が取れない場合は、コンテンツが掲載されているプラットフォーム(SNS、YouTube、ブログサービス、サーバー会社など)に直接削除を要請します。
DMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく削除申請
多くの海外発のプラットフォーム(Google, YouTube, Twitter/Xなど)は、米国の**DMCA**(デジタルミレニアム著作権法)に準拠した削除申請フォームを用意しています。
- フォームに必要事項(著作権者情報、侵害コンテンツのURL、元の作品のURL)を記入し、宣誓書にサインすることで、プラットフォーム側が侵害コンテンツを一時的に非公開にする措置をとってくれます。
- この手続きは、裁判を経ずにコンテンツを削除させる、非常に強力な手段です。
日本のプロバイダ(サーバー会社)にも、プロバイダ責任制限法に基づき、著作権侵害の削除請求を行うことが可能です。
ステップ5:専門家に相談し、法的措置を検討する
直接交渉もプラットフォームへの申請も効果がない場合や、大きな損害が発生している場合は、専門家である弁護士・弁理士に相談します。
- 損害賠償請求:無断利用によって失われた利益(本来得られたはずの利用料など)を請求する訴訟を提起します。
- 差止請求:侵害コンテンツの利用停止や、既に流通している複製物の廃棄を裁判所に求める手続きです。
- 発信者情報開示請求:匿名アカウントによる侵害の場合、プロバイダに対して、侵害者の氏名や住所などの情報開示を求める手続きです。
法的措置には時間と費用がかかりますが、悪質な侵害に対しては、クリエイターの権利を完全に回復させるための最終手段となります。
費用を抑えたい場合や専門家個人へのコンタクトが難しい場合は、法テラス等で無料相談から始めることもできます。
【まとめ】冷静沈着が勝利への鍵
著作権侵害を発見したときの最大の武器は、**感情ではなく証拠と手順**です。まずは冷静に侵害の事実を客観的に確認し、迅速に証拠を保全することが重要です。そして、交渉、プラットフォームへの申請、法的措置と、段階を追って対応することで、堅実に権利保護への道を進めることが必要です。
本記事は内容の一部にAI機能を使用しています。